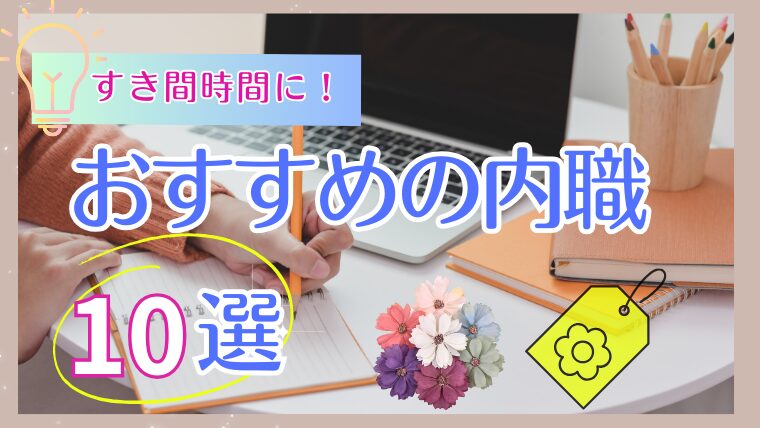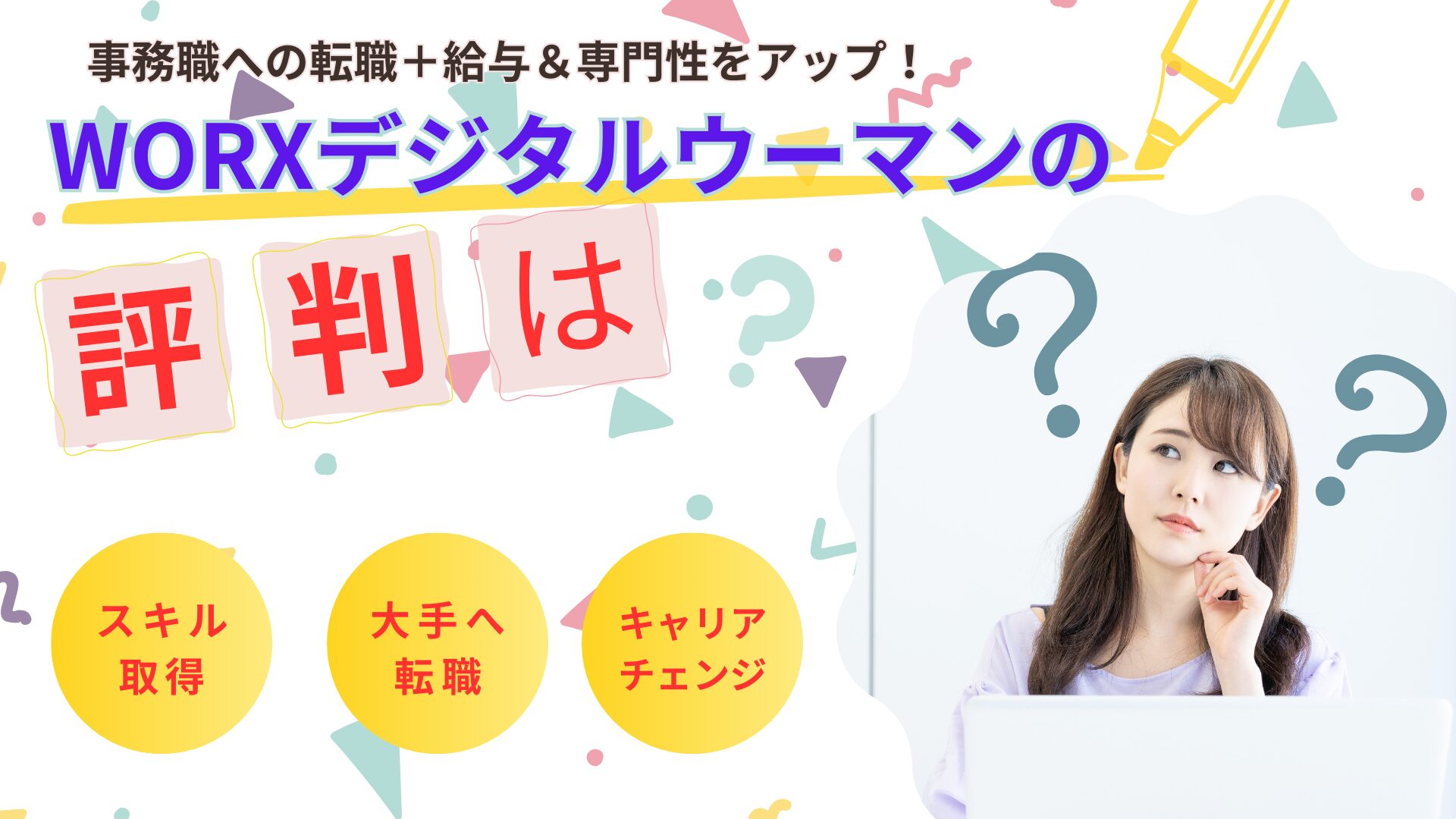ストレス社会の日本。人手不足から残業が続き「最近ちょっと体調が悪い」といった声もよく耳にします。
あまり無理をしすぎると慢性的な病気になるケースも多く、毎日の生活に支障をきたす可能性も。
もしあなたがそのような状況に陥ってしまったら、ぜひ「障がい者手帳」を持つことを検討してみてください。



この手帳は、主に精神的な疾患を抱えている方が対象。ちょっとハードルが高いと思うかもしれませんね。ですが、長い間、症状に悩みながら日々を過ごす中で、少しでもサポートを受けられる手段となるんです。
この手帳を持つことで、様々なサービスや支援を受けることができます。例えば、医療費が安くなることや、就労支援を受けられる可能性も!生活が少しでも楽になる手助けをしてくれるアイテムだということを知っておくことが大切です。
さらに、これからの転職にもよい変化が訪れます。
そこで、ここではもしあなたが「障がい者手帳」を検討したい場合の取得方法をはじめ、手帳を持つメリットと、おすすめの転職方法についてご紹介していきたいと思います。
障がい者手帳は「社会参加」を促すための潤滑油
厚生労働省の「生活のしづらさなどに関する調査」によると、20歳から29歳までの層では約8.7万人が手帳を持っていることがわかりました。
また、30歳から39歳までの層では8.6万人となっています。この数字は、全体から見ると低めに感じるかもしれませんが、数としては決して少なくはないんですよね。
20代から30代は、いろんなことに挑戦しながら毎日を過ごしていますよね。
ですのでこのデータを通じて、同じ年代の人たちがどんな現実に直面しているのかを知るのも大事なことかもしれません。
ではどんなメリットがあるのでしょうか。手帳の種類や等級、お住まいの地域によって受けられるサービスは異なりますが、主なものは以下の通りです。
税金の控除・減免
障がい者手帳を持つと、さまざまな税金の控除が受けられるようになります。



-
- 所得税・住民税の障がい者控除: 納税者本人やその配偶者、扶養親族が障害者の場合、所得から一定額が控除されます。特別障がい者(重度の障がい者)は控除額が大きくなります。
-
- 相続税の障がい者控除: 相続税が控除されます。
-
- 贈与税の非課税: 特定の信託金銭などについて、一定額まで贈与税が非課税になります。
-
- 自動車税・自動車取得税の減免: 障がい者や生計を同一にする方が所有・運転する自動車について、一定の条件で減免が受けられます。
医療費の助成
医療費などは毎月通うことで費用がかかりますが、これらのサポートも受ける事ができます。
-
- 自立支援医療費制度: 精神疾患の治療費や、更生医療、育成医療などの自己負担額が軽減されます。
-
- 心身障がい者医療費助成(マル障医療証など): 地方自治体による医療費助成制度です。
-
- 生活福祉資金貸付制度: 低所得者や障がい者世帯に対し、生活費や住宅費などの資金を貸し付ける制度です。
公共サービス・施設利用の割引・無料化



-
- 鉄道(JR、私鉄): 運賃が割引になります(本人単独または介護者同伴で5割引など、手帳の種類や等級、距離による)。精神障がい者保健福祉手帳については、2025年4月1日からJRグループで割引制度が拡充されます。
-
- バス: ほとんどのバス会社で運賃が割引または無料になります(手帳の種類による)。
-
- タクシー: ほとんどのタクシーで1割引が適用されます。
-
- 航空機・船: 国内線の運賃が割引になる場合があります。
-
- NHK受信料の減免: 一定の条件を満たす場合、全額または半額が免除されます。
-
- 携帯電話料金の割引: 各携帯電話会社が独自の割引プランを提供しています。
-
- 上下水道料金の減免: 地方自治体によっては、減免措置があります。
-
- 公共施設の利用料割引など
- 美術館、博物館、動物園、植物園、公園、レジャー施設などの入場料や利用料が割引または無料になります(同伴者も対象になる場合があります)。
- 体育館、プールなどのスポーツ施設も割引の対象となることがあります。
- 公共施設の利用料割引など
体調を理解されたうえでの就労が期待できる
転職活動にもサポートがあります。「障がい者手帳を持っている」専門採用への雇用が期待できます。



-
- 障がい者雇用枠での就職: 企業での障がい者雇用枠に応募できます。
-
- 就労移行支援、就労継続支援: 就職に向けた訓練や就労の場を提供するサービスを利用できます。
-
- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金: 障がい者を雇用する企業に対して、職場環境整備などのための助成金が支給されます(事業主向け)。
いかがでしょうか。
これらの福利厚生は、障がいのある方の生活をサポートし、社会参加を促進するための重要な制度です。
このように「障がい者手帳」という響きは「ちょっとドキっ」とはしてしまいますが、誰もが安心して暮らせる社会を目指す上で、重要な役割を果たしています。
障がい者手帳を取得できる人や申請方法
それでは、ここで「障がい者手帳」を持つ場合、申請の対象はどんな人なのかを理解しましょう。
令和7年(2025年)における障がい者手帳を取得できる人、およびその取得方法は、障がい者手帳の種類によって異なりますが、障がい者手帳には主に以下の3種類があります。
- 身体障がい者手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 療育手帳(知的障がい者への手帳)
もしあなたが「該当しているな」と感じていて、障がい者手帳を取得する、してみたいとお考えの場合、基本的な流れは以下の通りです。
医師の診断をあおぐこと
自身の障がいに関する診断書を、担当の医師に依頼します。診断書が必要となるので、障がいを証明できる病歴や症状の詳細が含まれている必要があります。
自治体へ申請すること
診断書をもって、住民票がある市区町村の障がい者福祉担当窓口に申請します。申請書類には、医師の診断書に加え、必要な書類(本人確認書類など)も含まれます。
審査と交付を行うこと
提出した書類に基づいて自治体が審査を行い、手帳の交付可否が決まります。審査には時間がかかることがあるので、数週間~数ヶ月程度の時間を見込んでおくとよいでしょう。
上記をふまえ、それぞれの取得方法を詳しく見ていきましょう。
1. 身体障がい者手帳の対象者
身体障がいなどを持つ方の手帳です。対象者は永続する身体上の支障がある方で、以下のいずれかの機能に一定以上の障がいがあると認められます。
-
- 視覚障がい 聴覚障がい
- 平衡機能障がい
- 音声・言語機能障がい
- そしゃく機能障がい
- 肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)
- 心臓機能
- じん臓機能
- 呼吸器機能
- ぼうこうまたは直腸機能
- 小腸機能
- 免疫機能
- 肝臓機能 など
手帳の取得方法
身体障がいにおける手帳の対象者であることが分かったら、以下のような手順で申請していきます。
- 相談・申請書類の入手: 市区町村の障がい福祉担当窓口(福祉事務所や福祉担当課など)に相談し、「身体障がい者手帳交付申請書」と「身体障がい者診断書・意見書」の用紙を入手します。
- 指定医による診断書の作成: 都道府県知事や指定都市市長が指定した医師(指定医)を受診し、診断書を作成してもらいます。かかりつけ医が指定医でない場合は、窓口で紹介してもらうか、指定医がいる医療機関を受診して診断書を作成してもらいましょう。
診断書は、申請書提出日から3ヶ月~1年以内の日付のものが必須です。書類が整ったら市区町村の障がい福祉担当窓口に提出します。
- 身体障がい者手帳交付申請書
- 身体障がい者診断書・意見書
- 顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身正面、申請日から1年以内に撮影されたもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)と身元確認書類
- 印鑑(自著の場合は不要な場合もあります)
提出された書類に基づき審査が行われ等級が決定します。交付までには、通常1ヶ月から4ヶ月程度かかります。
2. 精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳は精神疾患(知的障がいは除く)により、長い間日常生活や社会生活に制約がある方でが対象です。
-
統合失調症
-
うつ病(重度)
-
双極性障がい(躁うつ病)
-
パニック障がい、強迫性障がい
-
認知症
-
発達障がい(アスペルガー症候群、ADHDなど)
他
精神障がい者手帳の交付には、診断基準に基づいた精神科の医師の診断書が必要です。精神障がいにかかる初診日から6ヶ月を経過している必要があります。
手帳の取得方法
以下のような手順で申請していきます。
- 相談・申請書類の入手: 市区町村の障がい福祉担当窓口に相談し、申請書類を入手します。
- 診断書または障がい年金証書の準備: 以下のいずれかを準備します。
- 診断書による申請: 精神障がい者保健福祉手帳用の診断書を医師に作成してもらいます。診断書は精神障害にかかる初診日から6ヶ月を経過した日以降に作成されたものに限ります。
準備ができましたら、書類を市区町村の福祉担当窓口に提出します。
- 障がい者手帳交付申請書
- 診断書または年金証書等の写しと同意書
- 顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身正面、申請日から1年以内に撮影されたもの)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 印鑑(必要に応じて)
- 代理人が申請する場合は委任状や代理人の本人確認書類
提出された書類に基づき審査が行われ、1級・2級・3級の等級が判定されます。
交付までには約2ヶ月程度かかります。手帳は2年ごとに更新が必要です。
3. 療育手帳(知的障がい者への手帳)
対象となる人: 知的障がいのある方。原則として成長発達過程において生じるものとされていますが、18歳以上でも審査によって認定を受けられれば交付対象となります。
いかがでしょうか?
細々とした提出物が多いので、まずは医者に相談のうえご自身の状況に合わせて、最寄りの市区町村の福祉担当窓口に相談することをお勧めします。
大企業も「障がい者雇用」を積極的に採用
じつは大手企業も障がい者雇用に積極的に取り組んでいることをご存じでしょうか。
これは法的義務の遵守に加え、企業戦略上も多くのメリットがあるためです。
障がい者雇用のメリット
| メリット | 内 容 |
|---|---|
| 法令遵守・コスト回避 | 法定雇用率の達成、納付金の免除できる |
| 経済的支援 | 多様な助成金・報奨金制度などが期待できる |
| 組織の多様性と改善 | 働き方改革、コミュニケーション活性化 |
| 社会的評価・信頼 | CSR強化、ブランドイメージ向上を図れる |
| 戦力となる人材活用 | 障がい特性を活かした強みの発揮、業務改善の機会 |
それぞれみていきましょう
法令遵守・コスト回避
-
日本の民間企業では法定雇用率が企業規模に応じて定められており、達成できなければ不足1人につき月額約5万円の納付金が科されます。(例:従業員40人以上の企業)
-
大企業ほど納付金の負担は大きく、積極的な雇用によってコスト回避を図っています。
2. 経済的支援
-
さまざまな働き手を雇用することで、職場に定着させるための研修や設備投資に対して、国や自治体から助成金が支給されます。
-
特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金、キャリアアップ助成金など多様な制度があり、企業は経済的負担を軽減しながら障がい者への雇用に取り組めます。
3. 組織の多様性と改善



障がいのある方を含めた多様な人材を採用することは、柔軟な思考力や新たな視点が社内に生まれ、組織全体の活性化に繋がります。
これはすべての従業員にとって働きやすい職場づくりを考える事ができる、という点において魅力的です。
4. ブランドイメージとCSR評価の向上



障がい者雇用は企業の社会的責任(CSR)としても注目されています。
企業にとってもこの活動は、社会貢献度を示す具体的な行動とみなされ、公的案件などで加点対象となることもあり、取引先や消費者からの信頼向上につながります。
5. 優秀な人材の獲得と業務効率化
企業が「障がい者雇用」に積極的な理由として、発達障がいやHPS,自閉症などの方は、高い集中力や反復作業の精度に優れた特性を持つ人が多くいるからです。
これらの特性に合わせて業務を振り分けることで、業務効率の改善・生産性向上につながるため、獲得することが多いのです。
障がい者手帳を持った時の転職方法
それでは障がい者手帳を取得すると、どのような場所で求職活動できるのかをチェックしていきましょう。
主には以下のよう3つの方法があります。
1.ハローワークでの雇用(障がい者採用枠)
2.転職エージェントでの雇用
3.障がい者転職サポートでの雇用
障がい者手帳を持っていると、どこで求職活動をしていいか迷うこともあると思います。でも、実はサポートを受けながら仕事を探せる専門のサイトも増えてきました。
そこで、ここでは、おすすめの障がい者転職サポートをご紹介します。
おすすめ1.dodaチャレンジ



『dodaチャレンジ』は、障がい者のための専門的な転職支援を行っているサービスです。
履歴書の書き方から面接対策まで、親身になってサポートしてくれるので、初めての転職でも安心。
とくに就職後も職場に馴染むためのフォローが手厚く、安心して働ける環境を提供しています。自分に合った仕事を見つける手助けが、しっかりと受けられます。
詳しくはこちら → dodaチャレンジ
おすすめ2.マイナビパートナーズ紹介
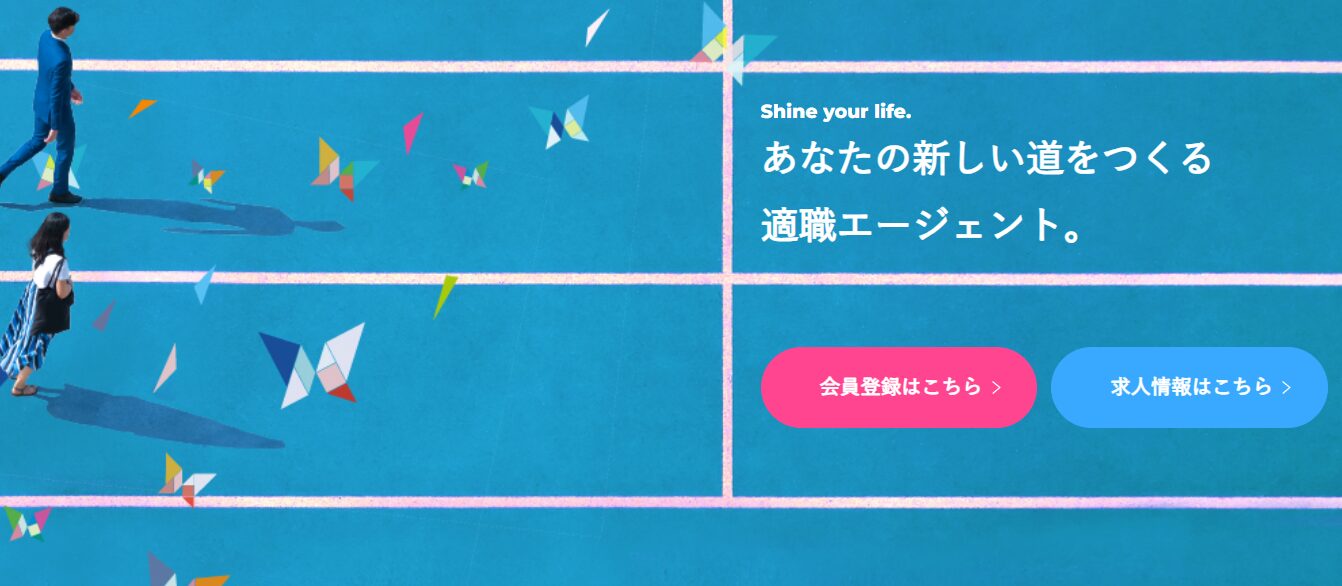
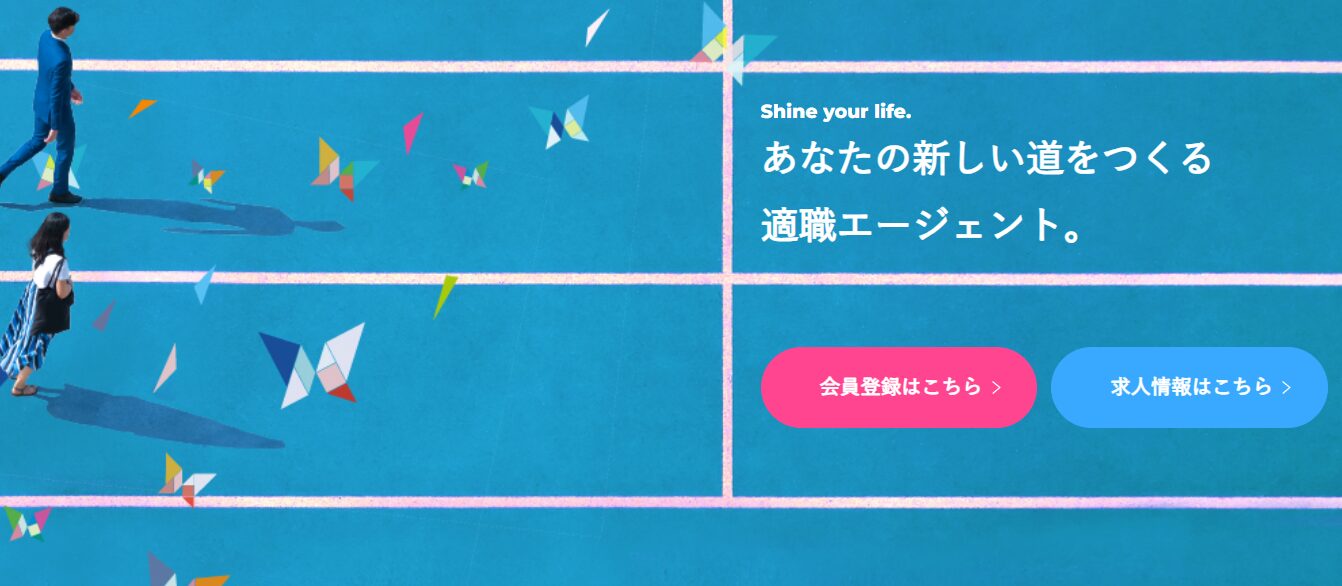
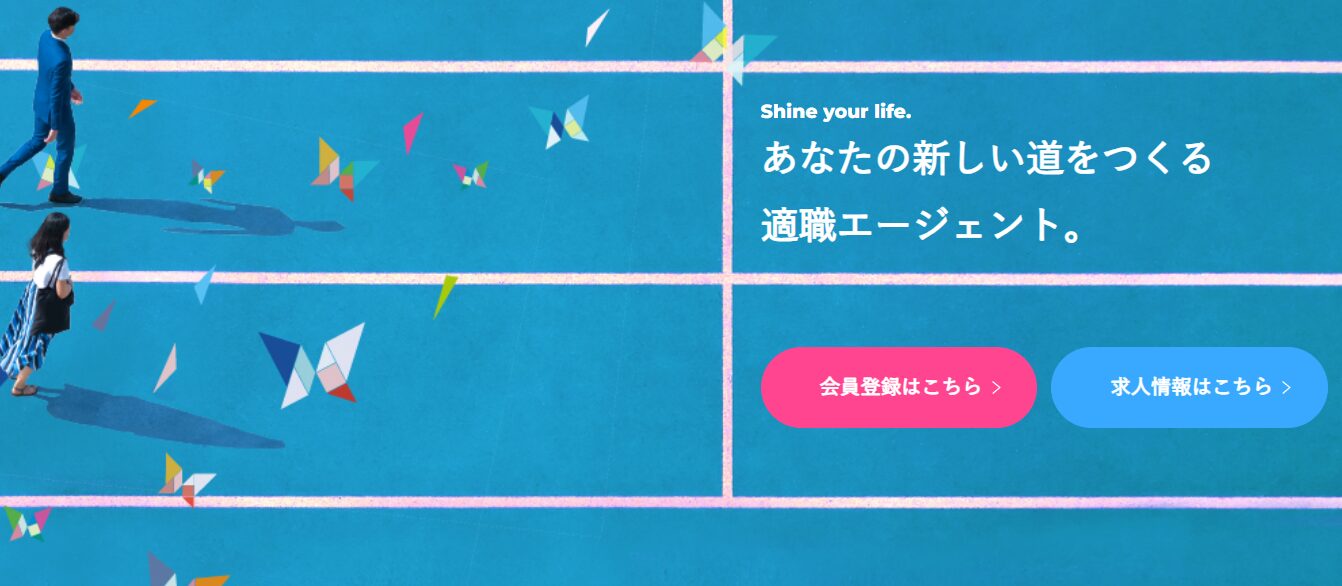
数多くの転職支援を行うマイナビ。マイナビパートナーズでは、その強みをいかし、マイナビ自信が特例子会社として雇用をサポートします。
事務、クリエイティブ等の業務を中心にサポートしていますので、在宅勤務や時間の相談など、あなたのニーズにぴったりな場所を探すのにもおすすめです。
気になる求人ですが、どのようなものがあるかをチェックしてみましょう。マイナビは全国展開しており、さまざまな業種があります。なかでもIT系、事務、クリエイティブ系が多く、その他の地域にも一定数の求人があります。
情報・通信業/卸売業/販売(通信)IT銀行業
人材サービス(派遣・紹介)/ホテル・旅行/冠婚葬祭/食品
商社/専門・その他サービス/マスコミ芸能・映画・音楽系など




そうですね。はやりクリエイティブな仕事や一般事務などが人気のようです。以下のようなものがありますので、ぜひ参考にしてみてください。
\ おすすめの仕事を探すなら /
![]()
![]()
![]()
おすすめ3.アットジーピー(atGP)



アットジーピー【atGP】は、障がい者専門の転職エージェントサービスす。
あなたの希望やライフスタイルに合った職場を一緒に探してくれます。
あなたが働きやすい環境を提供している企業とマッチングしてくれるので、ストレスなく仕事を始めることができます。障
がい者手帳を持つ方々に特化した、きめ細やかなサポートが魅力です。
詳細はこちら → アットジーピー【atGP】
![]()
![]()
![]()
障がい者手帳は返納できる?就業中に健康になったら
障がい者手帳を持っているけれど、いざ働きはじめると「元気になってきたから手帳を返納したいな」考えなおすこともあるでしょう。
実は、障がい者手帳の返納は可能です。この手帳は、あなたの障がいの状況や状態に応じて発行されるもの。だから、健康状態が改善したり軽くなったりすると、手帳を返すことができるんです。
もしも、自分の状況が変わったことを実感しているなら、思い切って手帳を返納することを検討しましょう。
自分自身の成長や変化に気づくことは、とても大切なことです。手順は主に以下の通りです。
障がい者手帳を返納する手順
-
自治体へ連絡する
-
手帳を返納したい旨を、居住地の市区町村の福祉担当窓口に連絡します。健康状態が回復した場合や、程度が変更された場合は、手帳の返納が必要です。
-
-
返納手続き
-
指示にしたがい手帳本体を返納します。自治体によって異なることがあるので、担当窓口で詳しい案内を受けると良いです。
-
-
医師の診断書が必要な場合も
-
健康状態が回復した証明として医師の診断書を求められることがあります。例えば、医師からの「障がいがなくなった」または「軽減した」という内容の証明書を提出することが必要な場合があります。
-
注意点
-
手帳返納後は福祉サービスなど、障がい者向けの支援を受けることができなくなります。
-
新たに支援が必要になった場合は、再度申請する必要があります。
-
障がい者手帳を返納しても完全に解消されたわけではない場合があるため、その後の生活に影響がないかどうかも確認しておくとよいでしょう。
病気が治った場合、企業の対応はどうなるか



いざ「手帳を返納したい」となった場合、企業とはどのような関係の変化があるか、気になりますよね。
以下のような流れが一般的ですが、詳細は企業の人事と相談してみることをおすすめします。
障がい者雇用枠から移行する
障がい者雇用の枠で採用されている場合、病気が回復して障害者手帳を返納したり、障害の状態が改善されると、企業がその社員を一般枠(障がい者枠ではない枠)に移行することがありえます。
企業が障がい者枠を維持するかどうかは、企業の方針やその社員の職務内容による部分も大きいです。
たとえば、職務内容が障がい者向けの配慮が必要なものであった場合、配慮なしで働くことができるかどうかが企業と社員との間で調整されることになります。
一般社員への移行
病気が治り、障がいの状態が改善されると、障がい者雇用枠ではなく、一般の従業員枠に移行する可能性もあります。
この場合、給与や待遇が一般従業員のものに変更されることが一般的です。
ただし、企業によっては、障がい者枠の待遇をそのまま維持するという選択肢を提供する場合もあります。
これには、個別の契約や職場環境に依存するため、上司や人事担当者としっかり話し合って確認することが重要です。
まとめ
ここでは障がい者手帳の申請やメリット。転職活動をする方法についてまとめてみました。
もしあなたが「ちょっと体調が悪いな」と感じていて、企業にアプローチする際に必要だと思ったなら、通院中のお医者さんに相談しながら申請してみるといいでしょう。
その他体調に関するコンテンツは以下でもご紹介しています。
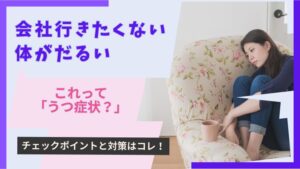
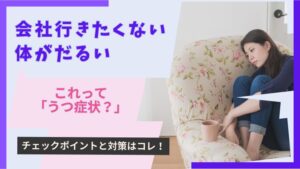
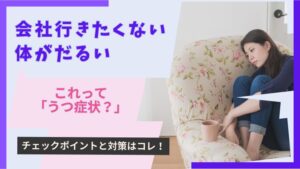
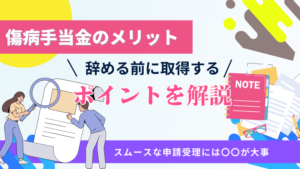
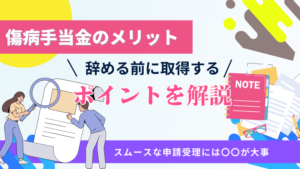
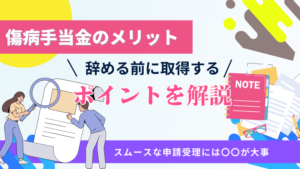
障がい者手帳を持つことで、あなたが挑戦してきたことや乗り越えてきた経験を強みにして、より自分らしいアピールができるはずです。
転職活動は時にプレッシャーがかかることもありますが、あなたには必要なサポートが揃っています。
障がい者手帳をうまく活用して、ポジティブな気持ちで企業との出会いを楽しんでくださいね。あなたの転職活動を心から応援しています!